日本で今、学校入学の時期を4月から9月に変えようという議論があります。
この議論自体に深入りはしないのですが、ふと自分が田舎から東京の大学に入って、何を学んだのかなと振り返ったりしました。
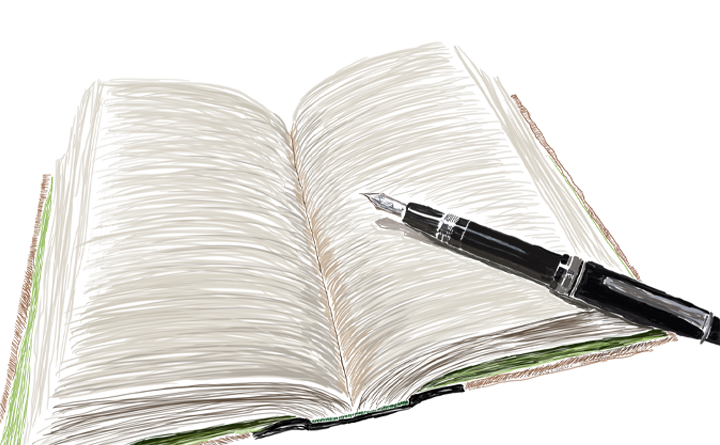
最初は大教室での講義ばかりで「なんてつまらないんだ」と幻滅したところからでしたが、面白い先生もいました。私は法学部だったのですが、ローマ法の木庭顕先生の授業では「僕の本も今は理解されないけど千年後くらいの学者が古典として評価するでしょう」とか言っていたし(同時に「皆さん、実際の業務でボーっと気を抜いていたらケツの毛まで抜かれますよ」とか言っていて面白かった)、近代法制史の和仁陽先生には色々な逸話が多かった(例えば、奥さんと一緒にイタリアオペラを見ていて、突然一緒に歌い始めたものだから奥さんが「あなた、イタリア語も話せたの?」と聞いたら「君はこんなに僕と一緒にオペラを聴いているのにイタリア語も分からないのか」といったとかどうとか。真偽は不明です。和仁先生とは個別にご飯も行って良くしてもらいました)。

大学の良いところは別の授業にも潜りこめるところで、高校生の時に読んだ『ラテン語の話』という本の著者であった逸身喜一郎先生のゼミに潜り込ませてもらったり(今でも憶えているのはギリシャ悲劇の原文講読をしながら(その時は確かエウリピデスのアルケースティスだった)、美味しいワインが出てくるシーンで「ワイン飲むって言っても、2000年以上前の話だから、今みたいなフルボディのすごいのじゃないよ」とか言っていたこと)、土田龍太郎先生のサンスクリット講座に一年間通わせてもらったことも良い思い出になっている。法学部のゼミは民法とか刑法とか国際法とか政治学といったものばかりだけれど、こっちの文学部生の会話は「今日、維摩経のゼミ出る?」とか「法華経のゼミ出る?」とか、法学部生にとってはもう何を言っているか分からない用語が連発されるので、その時点ですでにカルチャーショックと言うか、相当楽しかった。授業中に土屋先生が独特の響く声で「ここでラーマは敵の手を一本ずつ切り落とすのですが、敵の手も次々と生え変わるのでありまして、云々」という説明を必死でみんなメモをとっている、その光景も法学部生としてはもう異次元で楽しくて仕方なかったものでした(その後、土田先生とも年賀状のやり取りなどさせてもらっていて良くしてもらいました)。

大学の図書館の書庫もよくうろうろして楽しい時間でした。書庫をうろうろしていたら『熊野方言の研究』(だったか。正確な名前を憶えていない)、全10巻位の誰も読んでいなさそうな本があって、「こんな研究もあるんだ、ふーん」と(愚かにも)1年生の時は思ったものでしたが、いざ自分が修士課程で論文を書かなければと思った時にもう一度『熊野方言の研究』が目に留まり、「こんな立派な研究をした人がいるんだ」と非常に感動したのもよく覚えています(この変化だけでも大学に行った甲斐があるかもしれない)。そして、こういう研究が一つ一つ重なって人間の文化は発展していくのだ、と実感すると同時に、図書館の膨大な文献を前に立ち尽くし、絶望感を憶えたのも事実でした。大学の前には古本屋が一杯あったのですが、どの本も題名は分かる、興味もある、でも4年も6年も大学にいるのに全然手についていない、という事実にもまた、愕然として絶望を生むものでした。

一方でよく勉強はしました。しかし、やっぱりもっと勉強したかった、勉強できたのではないか、とも思っています。そういう奥深さに触れることができたのが、やはり大学という場所での一番の収穫なのかもしれません。そして歴史の中の自分の小ささを知り、学問というものの大きさを知ったというのが、大学での思い出なのです。

9月入学にしたらグローバル水準になるから留学しやすいなとかなんとか言っていますが、それは留学もしたことがない人間の妄想かなと思っています。大学の魅力はその大学の学問水準であり、魅力ある教授陣以外の何物でもありません。そこを高めていくのが、大学改革の本筋であり、ひいては国力に結びつくのだと思います。


