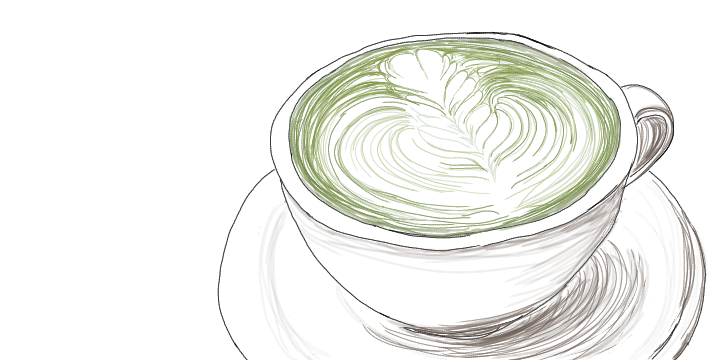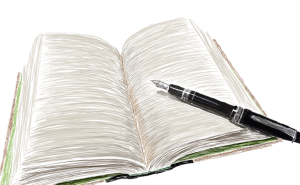■パーパス、MVV、そしてロゴス(言葉)至上主義
(1)はじめに
2010年代に入って「パーパス経営」という言葉が流行るようになりました。これはリーマンショックなどを踏まえて、利益追求よりも社会貢献的な姿勢が益々重要視されるようになってきたことが大きいでしょう。また、『シンギュラリティ大学が教える飛躍する方法(原題:
Exponential Organizations)』でサリム・イスマイルは「MTP:Massive Transformative
Purpose(野心的な変革目的)」が飛躍的成長には必須であると言っています。10X(テン・エックス)とも言いますが、「桁違い」の成長をするには無謀とも思えるような目標設定が必要だというのも分かる気がします。
(2)ミッション・ビジョン・バリューとその非合理性ゆえの強さ
もともと企業経営のなかでこういったテーマはミッション・ビジョン・バリュー(MVV)というフレームワークで語られてきました。もちろん経営理念や社是、綱領、クレドなど様々な言い方がありますが、MVVという3点セットが分かりやすいということで便利に使われています。
・ミッション(Mission):企業の存在理由、使命
・ビジョン(Vision):企業が目指す将来像、夢
・バリュー(Value):企業が持つ価値観、行動規範
パーパスとの関係で言うと、ミッションが「与えられた使命」というニュアンスがあるのに対し、パーパスはより主体的に「自分で設定した目的」という意味合いが強いと言われます。実際、ミッションは「神と自分との関係性」という印象がある一方で、パーパスは社会的意義を訴えることが多く、「社会と自分との関係性」に焦点を当てているイメージがあります。ただ、広い意味では同じでもあり、無理に区別する必要はないように思われます。
このミッション・ビジョン・バリューは3点セットでのフレームワークを誰かが提唱したわけではなく、長い企業研究の歴史の中で自然と紡ぎだされてきました。「マネジメントの父」といわれるP.F.ドラッカーがその著書『マネジメント』のなかでミッションの重要性に触れたのが1974年、コンサルティング会社であるマッキンゼーのトム・ピータースが『エクセレント・カンパニー』で優れた企業の特徴として「基本的な価値観(バリュー)への固執」を挙げたのが1982年、経営学者であるジム・コリンズが『ビジョナリー・カンパニー』で「偉大な企業の原動力はビジョンである」だと指摘したのが1994年でした。そういった機運の中で、経済合理性ではない「何か」が超優良企業を生み出す礎になっているということが分かってきて、MVVというフレームワークに結集したと言ってよいでしょう。従って、本来はこの3つはそれぞれが独立したものであり、重なり合い、自社のこだわりをどう定義するか、そしてどのように人々を動機づけるかという方法論の問題であると言えるのかもしれません。
『エクセレント・カンパニー』のなかで、トム・ピータースは以下のように言います。
—--
冷徹な合理主義をもって、超優良企業が“超”たるゆえんを説明することはできない。顧客を大切にすることの真の意味合いも教えてくれない。なにより重要な任務はごく平均的な人間の潜在能力をトコトン使い、負け知らずの英雄にすることだということも教えない。それは、ちょっとした助言をしてやるだけで、労働者がどれほど自分の仕事に一体感を抱くかを示してはくれない。自発的な品質管理の方が監督者に依存した品質管理よりはるかに効果的なのはなぜか、という問いにも答えてくれない。
(第2章 合理主義的な考え方)
—--
興味深いことは、世界的に有名なコンサルティング会社であるマッキンゼーがこのような洞察をしている点であり、その「非合理的なところ」にこそ近年でいう「人的資本経営」のポイントがあるのだろうということです。
ゴールデンサークルで有名なサイモン・シネックはTEDの講演である「優れたリーダーはどうやって行動を促すか」において、このような「非」合理性によって心が動くのは「心理学ではなく生物学だ」と指摘しています。脳の構造上、言語を理解する大脳新皮質ではなく、より古い脳であり感情や信頼を司る大脳辺縁系を刺激するからこそ人は心を動かすのだということです。科学的な根拠は横においても、私たち自身、様々な経験からそのような事実は身をもって体験していると言えるでしょう。
(3)日本での導入の難しさ ~「言葉通り」を徹底する
一方、このミッション・ビジョン・バリューをそのまま日本に導入することには難しさもあります。
ミッション・ビジョン・バリューを掲げる会社は多いものの、どれだけの社員がそれを真剣に受け止め、自分の信条として肚落ちさせているでしょうか。ミッション・ビジョン・バリューで成功している会社は、とにかく「文字通り」その文言を受け取り、徹底してそれを突き詰めているからこそ成功しているのです。Googleはミッション通り「世界の情報を整理し、普遍的にアクセス可能で有用なものにする」を徹底させ、Amazonは「地球上で最も顧客本位の企業であること」を徹底しています。
マッキンゼーでは大前研一氏がアジア人で初めてディレクターに就任したとき、「米国」と「海外」で分けられている社員名簿を見て「これはOne
firm(1つの会社)というバリューに反する」と指摘し、実際、それ以降マッキンゼーの社員名簿はアルファベット順になりました。「海外(Overseas)」という概念は「世界中どこで採用されてもマッキンゼーの社員というクオリティは変わらない」というOne
firmというバリューとは相容れないとされたわけです。当然、マッキンゼーは合弁会社も作りませんし、日本法人のような別会社も造りません(支社という位置づけ)。それはOne
firmに反するからです。
このような「文字をそのまま文字通り受け止め、徹底する」というある種のサイコパス性が求められるからこそ、突き抜けた実績につながります。そして、ミッション・ビジョン・バリューやパーパスで成功している企業には米国系の企業が多いと思いますが、それは多国籍が交じり合う中で「言語」に依存しなければ合意形成できない、逆に「言語」の持つ重みが非常に強い社会ならではといえるでしょう。「契約書にはこう書いてあるけど、実際はそんなこと言わないよね」的な発想のある日本とは似ても似つかない世界なのです。
この言語にこだわる価値観はユダヤ系に見られる契約至上主義に端的に現われています。シェイクスピアのヴェニスの商人という喜劇がありますが、簡単にあらすじを追えば、貿易商であるアントニオがユダヤ人の高利貸しであるシャイロックから借金をしたうえで、商戦が難破したために返金ができなくなる話です。担保はアントニオ自身の胸の肉1ポンド(500g)となっており、全財産を失ったアントニオにシャイロックはあくまでも証文どおり返済を迫って裁判に訴えます。どこまで慈悲を諭されても「証文(契約書)通りに」と譲らないシャイロックに対し、最終的に裁判所は肉1ポンドを切り取ることを認めることになります。ただし、
「証文には1ポンドの肉とはあるが、血のことは書いていないぞ。
もし一滴の血でも流そうものなら、所有地も財産も没収する。また、肉が1ポンドより多くても少なくても相成らぬ」
と条件をつけるのです。それまでは「証文通りに」と譲らなかったシャイロックですが、逆に証文を逆手に取られて、この劇は落着に向かいます。強欲に見える高利貸しシャイロックが成敗されてめでたし、という内容です。
ここでのポイントは、全ては契約書の解釈として劇中の攻守が構成されているということです。そして、これを私たちの多くは悪人シャイロックの成敗話として見るわけですが、ユダヤ人側からみたらどう見えるでしょうか。故・渡部昇一は架空の話として、ユダヤ人から見たときの教訓はこうであろうと、以下のように書いています。
—--
この不愉快な劇をみんなは喜劇だと言っている。しかし、われわれユダヤ人にとっては、これは悲劇以外の何ものでもない。相手が憎いからと言って、殺人にもなるような契約書を作るのは、そもそも金貸しの道に背くことだが、あの契約書には技術的な欠陥がある。切り取る肉の重さについては誤差を許容した書き方をしなければならない。また血が流れることは分かっているのだから、それも当然契約書に含ませておかねばならなかったのだ。シャイロックをいじめたヴェニスの商人や法廷もけしからんし、それに拍手する観客も不愉快だ。しかしシャイロックも悪い。ユダヤ人はあんな脇の甘い契約書を作ってはならないことをよく覚えておくがいい。
(渡部昇一「まさしく歴史は繰りかえす-今こそ『歴史の鉄則』に学ぶとき」)
—--
ミッション・ビジョン・バリューを成功裏に用いようと思えば、この感覚を持たねばなりません。そして、ハイコンテクストな社会である日本ではそういう発想は持ちづらいのです。
江戸時代の儒学者である佐藤一斎は政治家のあり方として、
当に人情を斟酌して、之が操縦を為し、之を禁不禁の間に置き、其れをして過甚に至らざらしむべし
(政治家は、人心の向う所をよく酌みとって適当に処理し、禁ずるような禁じないような状態にして、偏り過ぎないようにすべきである)
『言志四録』
と指摘していますが、「禁不禁の間」に置くといった発想をもつ国でいかにミッション・ビジョン・バリューという言葉を徹底して導入するか、よく考えたいところです。